Clik here to view.
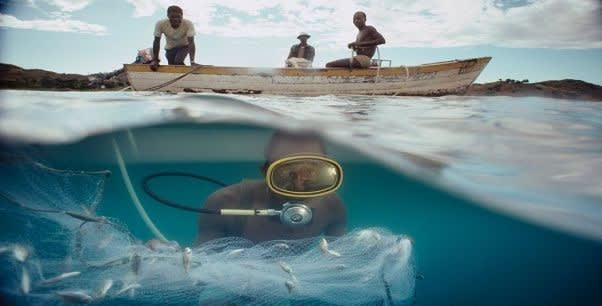
ⰧⰊⰧ Intermiussion/幕間 =狂(きょう)の出来事=平成5年02月06日<ⰧⰊⰧ
☆★ マンチェスター・ユナイテッドが試合開始より遥か前に飛行機でオウンゴール、主力選手が強制的にこの世から退場させられる(1958年)。☆★ 日の丸飛行隊がまさかの飛行成功、オリンピックで金銀銅独り占めする事態に(1972年)。 &so 視聴者を恐怖のどん底に叩き落とすことになる地獄少女が、地獄の底から現世へと甦る(1980年)。☆★ 作家宮本百合子の旦那が、浜田幸一によって国会で人殺しに認定される(1988年)。ハマコウ公言/“昭和8年12月24日、宮本顕治ほか数名により、当時の財政部長小畑達夫を股間に……針金で絞め、リンチで殺した。” このことだけは的確に申し上げておきますからね。
本日記載附録(ブログ)
「自らロボットを作り、さらにそれを無限に改良していくロボット」の研究論文で脚光
レントゲン、アインシュタインなどが学んだチューリッヒ大学・バイオロボティクス研究室ディレクター
「生物にアイデアを得たロボット」を研究している飯田史也教授
【この企画はWebナショジオ】を基調に編纂(文責 & イラスト・資料編纂=涯 如水)
若いうちに違う見方をしたい、と “ロボット大国”日本をあえて飛び出した
飯田史也(11) ◇◆ 第5回 ロボットは脳がなくても歩けるんです! =2/2= ◆◇
動画資料-3- 世界最高レベルの効率を誇るホッピングロボット https://youtu.be/1bYzkgBdvZ0
この場合、共振を起こすモーターの機構が振り子で、たわんだ足の構造がバネということになる。振り子とバネの仕組みである歩行をできるだけシンプルにしたもの、ということだろうか。
「なにがおもしろいかというと、モーターすら取り去った単に大きなオモリをバネの上に載っけてあげるだけで、坂をひとりでに降りていくことができるんです。これがまさにさっきの脳のないロボットにつながってくるわけですよね」
さらに、モーターによる共振を使った場合も、極端にエネルギー効率がよいので、こんなことができると、デモンストレーションの動画を見せてもらった。せいぜい手のひらくらいの大きさの太陽電池を背負ったロボットたちが、動き回っていた。
「──ソーラーパネルって、ものすごいエネルギー効率が悪いですけど、ロボット自体の効率がいいので、たったこれだけの面積のソーラーパネルで動くんですね。さっきの坂道を下るものとは違って、これはモーターを使った共振が入ってるので、坂を下らなくてもよいし、多少の坂なら登れるはずです」
「──生物に興味があるロボット学者は、生物学的な動きを見せるためにどうしたらいいかと、いろいろ研究しているんですけど、その中でも、我々が見せたいのはやっぱり、体の重要性がどれだけあって、体をつくるだけでいろんなことができるということなんです。実は、こういう研究、学生さんは大好きでして、原理は本当にものすごい簡単、多分これ以上ないっていうぐらい簡単な制御のメカニズムを使って、多様な運動を見せてくださいという課題を出すと、こういういろんなロボットをつくって持ってくるわけです」
動画資料-4- 坂をひとりでに降りていく超省エネルギーロボット https://youtu.be/PRTZIC_KnbE
飯田さんがチューリッヒ工科大学で創り出した「バイオ・インスパイアード」なロボット研究の流れは、しっかりと学生たち、ポスドクたちに受け継がれつつあるようだ。ぼくが訪ねた時のワークショップは、各種工作機械だけでなく、3Dプリンタまで完備され、学生が試したいアイデアをすぐに試すことが出来る態勢が整っていた。
研究における生産性の革命がこんなところでも起きている?
と思いきや、飯田さんは笑いながら、こんなふうに付け加えた。
「実はこうやってちゃんと動くロボットの背後には、何百というロボットの屍があるんですけど(笑)。オモリが上に載っかって、足を軸にした振り子になっているだけの単純な構造ですが、その振り子が2重・3重になってきたときにどうやって制御するか、実はすごい難しい問題なんです。振り子がいくつも絡んでくると複雑系の問題になってしまうので。生物たちはいとも簡単にそれをやってるわけですけども、我々がやるときは、ものすごく簡略化して、複雑系の問題を全部すっ飛ばして99%分かったとしても、それでもなお残りの1%はどうしてそうなっているのか分からないというような状況です。エネルギー効率のよいロボットで、世界に貢献したいと思い、1日でも早く実用に投入したいですけど、まだ、やっぱりよくわかんないんですよね」
次回は“第6回 自ら3Dプリンタを操り成長する究極のロボット”に続く
Image may be NSFW.
Clik here to view.
…… 参考資料: ケンブリッジ大学・飯田史也准教授インタビュー(前編/その弐) ……
対象にレタスを選んだのはなぜか?
−−今回取り組んだレタスを選ばれた理由、そして収穫するところで様々な要素分解をされたと思いますが、どのような部分がキーポイントだったか、あるいはうまく行かなかったかを教えてください。
我々は5年くらい前までは全く農業のことを知らなくて、この5年間本当に手探りでどこをつついたら何が出てくるのかということをずっと試行錯誤してきました。今回レタスの収穫のロボットがメディアに取り上げられたのも本当にたまたまです。現在、5〜10個くらいのプロジェクトを進めていて、その中のひとつが論文として発表され、メディアに取り上げられて知られるようになりました。
「収穫」というのは比較的誰にでもわかりやすい問題ということで、レタスに限らず、他にもアスパラガス、ブロッコリー、イチゴ、リンゴなどのリクエストがあるごとに試してみてはいるのですが、レタスはその中でも特に難しい。まず見た目でレタスは複雑な形をしていて、柔らかく、とても扱いが難しい。ロボット技術としても非常に面白いので、これが論文として発表されたということです。
レタスも成功率はまだまだ低くて、論文に出るレベルではあるのですが、成功しているといえるかはまだ分かりません。
ロボティクスは食料の生産・加工・流通・廃棄の問題に貢献できるか?
−−他にはどのようなプロジェクトを進めていますか?
周辺の研究室の人たちと共同で研究しているのですが、農業・食用加工ロボティクスセンターというプロジェクトが今年から始まりました。農業・食用ロボティクスに関連するあらゆることを研究います。
ロボティクスが食料の生産に対してどのような貢献をする可能性があるか、全般的に見ています。それこそ農業では作付けから収穫まで様々なプロセスがありますが、その後のサプライチェーンでは、どのようなロボットの使い方があるか。そして食料品加工、小売もあります。これらが全部繋がって食料問題の話になってくるので、全体として見たときにロボットがどこに入っていくのかが我々の興味です。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
== ロボティクスは食料の生産・加工・流通・廃棄の問題に貢献できるか?= =
できる限り今確立している技術を使って問題解決する
−−今回の論文でいわゆる人工知能といわれるものはレタスの認識や場所の推定になると思うのですが、他にはどのような技術を使われていますか?
ロボットと人工知能は分けなければいけないと思うのですが、人工知能の中にも、コモディティがあるものと、もうちょっと根本的な問題の人工知能とで分かれます。
ここでは主に産業化を目指しているので、基礎研究のところで5年、10年で役に立つものを作るのは難しい。できる限り今確立している技術を使って、どのように今まで解決していなかった問題を解決するかというのがこのプロジェクトにおけるスタンスです。その上で、今コモディティになっている、いわゆるビックデータ、ディープラーニングとかは、学部の学生さんでも1、2週間ちょっとチュートリアルをやれば使えるレベルにまでなってきています。これは5年、10年前はなかった技術なので、そういったものを積極的に使って何ができるかというのを試してもらっています。
一番わかりやすい例として、ビジョンを使ってたくさんデータを集めて、それをラベリングして、それさえできれば大抵のことは認識できるようになるというのが非常に面白いなと思っています。その技術だけをとっても様々な役に立つ場面があるというのが、ひとつの可能性になります。
・・・・・・明日(「イギリスのAI事情」)に続く
Image may be NSFW.
Clik here to view.
== できる限り今確立している技術を使って問題解決する ==
⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡
=上記本文中、変色文字(下線付き)のクリックにてウイキペディア解説表示=
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
前節へ移行 : https://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/308b865a02945cb0da77a839984697e3
後節へ移行 : http://blog.goo.ne.jp/学究達=389=/xxx
----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------
【浪漫孤鴻;時事自講】 :http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/
【壺公夢想;如水総覧】 :https://thubokou.wordpress.com/
================================================
森のなかえ
================================================